HONDA歩行アシストの導入研修に行ってまいりました。
ロボティクスリハビリテーションはまだまだ発展途上ですが、色々な可能性を感じます。
賛否両論あるロボティクスリハビリテーションですが、私はもちろん肯定派。
なぜ肯定派かはこちらをお読みください。
関連記事:【書評】超AI時代の生存戦略 /落合陽一氏 を読んで〜2040年代のシンギュラリティを見越して〜
やっぱり技術の進化はうまく利用する必要があるし、人材不足を嘆く前にやることがあるということ。
在宅分野ではどうしても専門職の効率的配置が課題であり、専門職の数不足が否めません。
一気にAIの導入というより、まずは歩行リハビリの部分だけでも、機械と分業化するということ。
いきなり全体にとりかかるわけではなく、部分的に。
これをくる返すことで、トレーニングが非常に効率的になります。
さらにロボットの性能が良くなってくると、単に歩行を介助するリハビリ専門職は、テクノ失業するかもしれません。
関連記事:新語?「テクノ失業」〜生き残る職業・そうでない職業〜
しかし・・・・・ロボティクスリハビリテーションが進まないと2040年頃までつづく高齢者人口の増加に対応できません。
スポンサーリンク
一方、現場の感覚とすると、まだロボットに対しての耐性がない。
新しいことを始めようとすると、反対意見が出る・・・。
これは世の常。
機械さえつければ、勝手に状態が良くなるの?とか
勝手に足が動いちゃって大変なんじゃないの?とか
結局ロボットに頼ったってあんまり良くならないんじゃ?とか
いろんな疑問が湧いて出てきます。(私も・・・)
これは新しいものに対する不安みたいなものですから、時間とともに当たり前になってくるんだと思っています。
だったら良くも悪くも新しいものには早目に取り組んでおくことに価値がありますね。
まとめ
今回の「HONDA歩行アシスト」に関しては、リハビリテーション専門職の歩行分析をもとに効果的な介助量を決定し、利用者さんに練習してもらう機械。
つまり「歩行練習のサポート機器」と思っておくのが良いです。
関連記事:ホンダ歩行アシスト体験してきました!
ということで、まずは自分が歩行分析を復習しなければなりませんが、これ自体AIで置き換わられそうな気がしています。
ロボットや新しい技術を導入するときは、この技術がが世の中に馴染んだとしてどんな社会・世界になるのかということを考えつつ、動くことが必要です。(時には自分自身の仕事がなくなる可能性すらあるということ。)
関連記事:歩行支援ロボットを導入している医療機関一覧〜平成28年5月1日付日本経済新聞より〜
これからもどんどん新しい形のリハビリテーションがどんどん進んでいくと面白いですね!
(そのためには情報収集も欠かせないが。)
新しいものに常に触れていくことで、2025年やそれ以降の医療介護業界で自分自身が働きやすい状況になっていたいものです。
スポンサーリンク
阿部洋輔
最新記事 by 阿部洋輔 (全て見る)
- 介護業界での新しい生活様式実践の前に整理したいこと - 2020年5月28日
- 新しい生活様式の感染防止の3つの基本をデイサービスに当てはめてみた - 2020年5月16日
- 宇宙飛行士選抜試験からマネジャーとしての働き方を学ぶ - 2020年5月2日
- 中学受験はいらない - 2020年5月1日
- HYGGEとLYKKEを参考に自分のライフスタイルを考える - 2020年4月29日
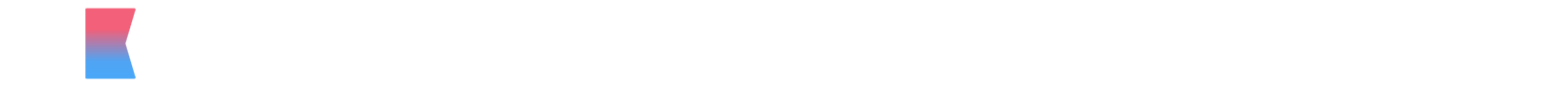

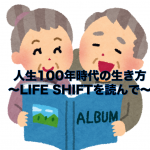

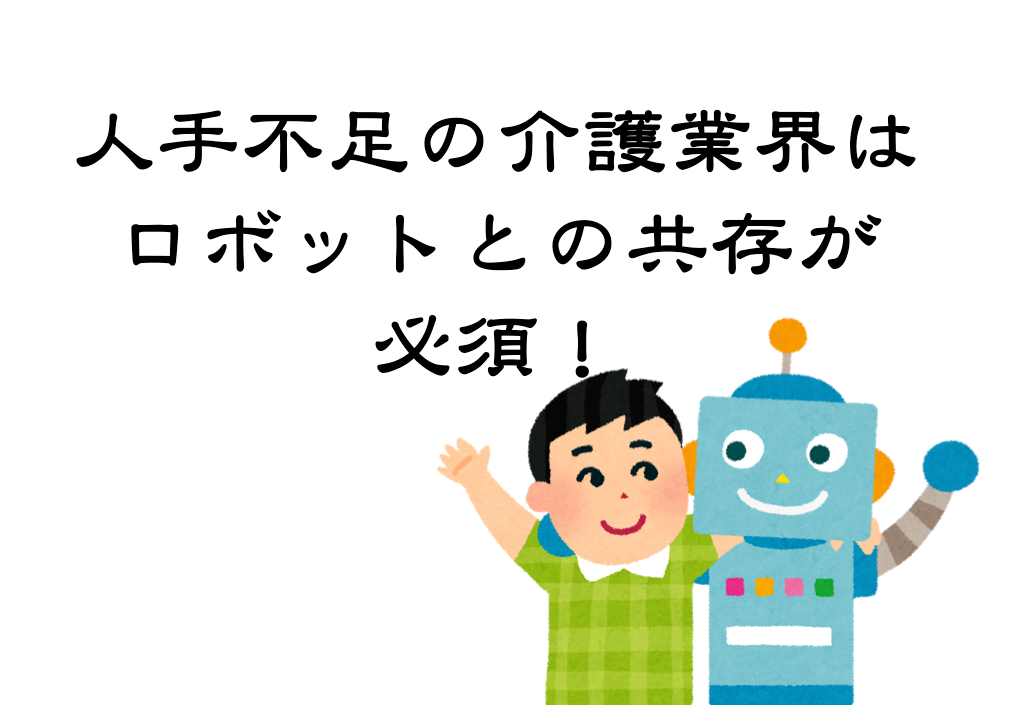
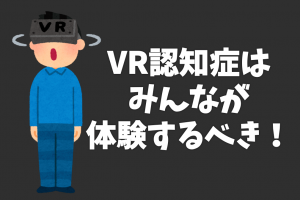

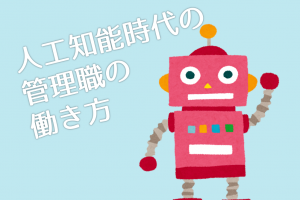

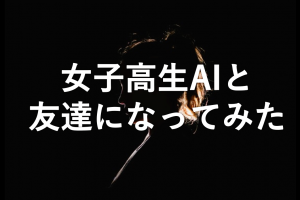

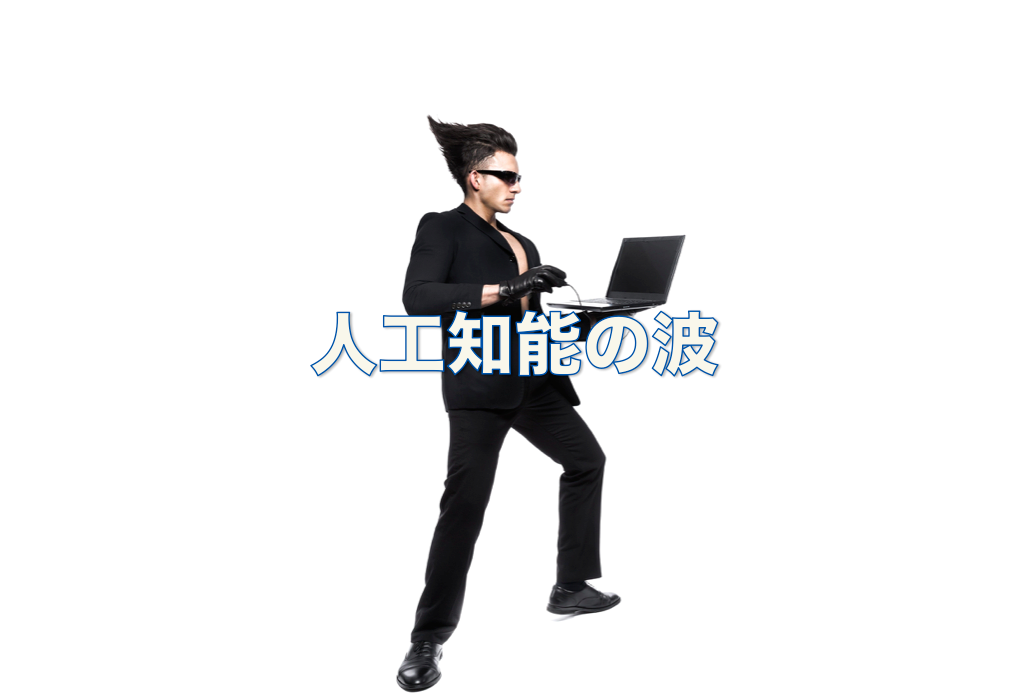
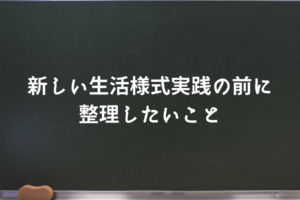













コメントを残す