スポンサーリンク
生活不活発病(廃用症候群)ってなに?
リハビリはどんなことに気をつけるのか?
気になる方に向けて記事をまとめました。
目次
生活不活発病(廃用症候群)とは
災害や体調不良などをきっかけに生活が不活発になり、体を動かさない状態が長く続くことで心身の機能が低下する症状を指す通称。
医学用語では「廃用症候群(はいようしょうこうぐん)」と呼ばれる。
特に高齢者、障害や持病のある人、災害によって極度に不自由な生活を強いられている人に起こりやすい。
発症すると、筋力の低下や関節の硬化を始め、骨の萎縮、心肺機能・消化器機能の低下、自律神経の機能低下、知的活動の低下、うつ状態など、心身に様々な症状が現れる。
一度発症すると慢性化しやすいため、生活の活発化や早期発見によって予防・回復を図ることが重要とされる。
災害による生活不活発病については、日本では2004年の新潟県中越地震で初めて認識され、11年の東日本大震災発生後にも多発したことから、厚生労働省や日本理学療法士協会などが注意を呼びかけている。
(引用:コトバンクより)
医療介護職は廃用症候群として習っていますが、最近は「生活が不活発である」という原因と、予防・改善には「生活の活発化を図る」という関係性が分かりやすい「生活不活発病」という用語が適切だという流れになってきているようです。
提唱者の大川弥生先生の書籍
この大川先生の新書は読みやすいので非常にオススメです。
生活不活発病の症状
体の一部に起きるもの
- 関節拘縮
- 廃用性筋萎縮・筋力低下・筋持久性低下
- 廃用性骨萎縮
- 皮膚萎縮(短縮)
- 褥瘡(床ずれ)
- 静脈血栓症→肺塞栓症
全身に影響するもの
- 心肺機能低下
- 起立性低血圧
- 消化器機能低下a.食欲不振b.便秘
- 尿量の増加→血液量の減少(脱水)
精神や神経の働きに対して
- うつ状態
- 知的活動低下
- 周囲への無関心
- 自律神経不安定
- 姿勢・運動調節機能低下
など非常に多くの部位に影響が及ぶことがわかります。
生活不活発病の悪循環
動かない➡︎生活不活発病➡︎動きにくい➡︎動かない
生活不活発病の良循環
よく動く➡︎生活不活発病が軽くなる➡︎動きやすくなる➡︎よく動く
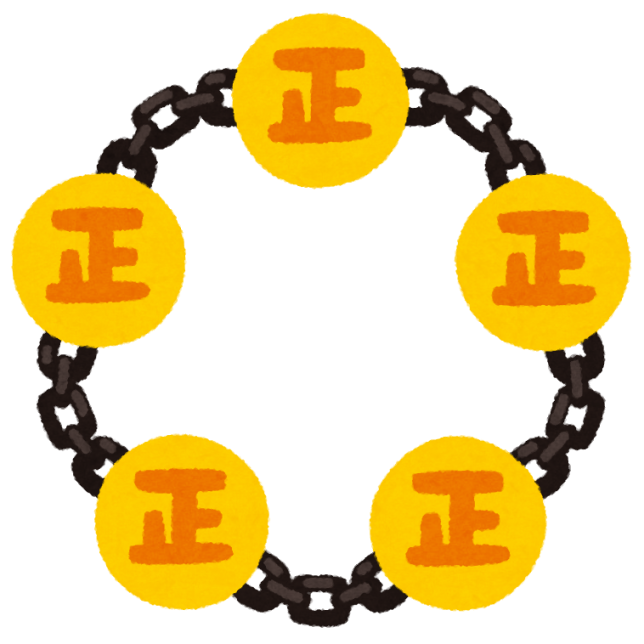
生活不活発病の予防・回復には
生活を活発にする
先ほどの生活不活発病の良循環を使います。
「生活を活発にすること」です。
生活が不活発なのだから、活発にしようという考え方。
なんてわかりやすい・・・・。

「活発にする」と言ういうと、特別に筋トレで腕立て100回とかそういうことではありません。
生活不活発病では多くの機能が同時に低下しますので、一部の機能だけに焦点を当てても解決ができません。
「筋トレ」のような運動を短時間行うよりも、1日全体の合計の活動量を増やす方が効果的です。
生活を楽しみ、社会に参加し、生きがいのある充実した生活を送ることが大事。
簡単に言ってしまえば「動く目的」を作ってしまうこと。
その点では在宅介護を受けている方にはデイサービスが一つの手段となることもあります。
専門家との連携
生活を活発にするためには普段の状態がわかっていないと始まりません。
そういった時には、専門職と連携して進めるとスムーズに進むことが多いです。
理学療法士・作業療法士などリハビリ専門職やデイサービスや訪問リハビリのスタッフに
- いつもはこんなやり方をしている
- 頑張ればここまでできる、工夫したらここまでできる
- 本人や家族が工夫していること
を情報提供できると非常に良いです。
なんでもやってあげてしまう介護の功罪
できることは自分でお願いする。
できない部分だけ介助する。
生活を活発にするにはこの考え方が非常に大切。
介助する時も、ご本人が今後やりやすくなるように介助する。
これが専門家だけでなく家族にも求められる時代になってきています。
スポンサーリンク
親切な気持ちで行う「不親切」が重要
リハビリはやってもらうものではなく、本人がやるものだと言う認識が重要。
介護もなんでもやってあげる介護ではなくて、その本人の能力なり機能をよくする方向へ導く介護がスタンダードになってきます。
そういった意味で、本人ができることは、「あえて手伝わない(不親切)」と言う親切心が大事です。
生活不活発病チェックリスト
厚生労働省がチェックリストを出しています。
参考にしてみてください。
1.屋外歩行
災害前 □遠くへも一人で歩いていた □近くなら一人で歩いていた □誰かと一緒であれば歩いていた □ほとんど外は歩いていなかった
現在 □遠くへも一人で歩いている □近くなら一人で歩いている □誰かと一緒であれば歩いている □ほとんど外は歩いていない
2.自宅内歩行
災害前 □一人で歩いていた □伝い歩きもしていた □誰かと一緒であれば歩いていた □ほとんど歩いていなかった
現在 □一人で歩いている □伝い歩きもしている □誰かと一緒であれば歩いている □ほとんど歩いていない
3.その他の生活行為(食事、入浴、洗面、トイレなど)
災害前 □不自由はなかった □不自由があった(具体的な行為:
現 在 □災害前と同じ □災害前よりも不自由になった(具体的な行為:
4.車いす
災害前 □使用していなかった □主に自分で操作 □主に他人が操作
現 在 □使用していない □主に自分で操作 □主に他人が操作
5.歩行補助具・装具の使用
災害前 □使用していなかった □屋外で使用 □屋内で使用 [種類: ]
現 在 □使用していない □屋外で使用 □屋内で使用 [種類: ]
6.外出頻度(30 分以上の外出)
災害前 □ほぼ毎日 □週3回以上 □週 1 回以上 □月 1 回以上 □ほとんどしていなかった
現 在 □ほぼ毎日 □週3回以上 □週 1 回以上 □月 1 回以上 □ほとんどしていない
7.家事 災害前 □全部していた □一部していた □ほとんどしていなかった
現 在 □全部している □一部している □ほとんどしていない
8.家事以外の家の中での役割
災害前 □全部していた □一部していた □ほとんどしていなかった
現 在 □全部している □一部している □ほとんどしていない
9.日中活動性
災害前 □よく動いていた □座っていることが多かった □時々横になっていた □ほとんど横になっていた
現 在 □よく動いている □座っていることが多い □時々横になっている □ほとんど横になっている
このチェックリスト自体は災害に被災した時のためのもんではありますが、 ちょっとしたきっかけでも生活不活発病になるリスクが潜んでいるので、ぜひ確認してみてください。
まとめ:間違った善意が生む生活不活発病
これだけまだ一般には理解されているようで、理解されていないこの生活不活発病。
間違った認識や、間違った善意がさらに状態を悪化させてしまうこともあります。
決して専門職が行う「機能訓練」や「リハビリ」だけが解決策ではないのです。
家事を行ったり、できることを自分自身でやることですら立派な方法なのです。
なんでもやってあげてしまうことは、その方の生活を不活発にしてしまう要因にもなります。
先ほど紹介した大川先生の書籍の中にも、被災地でのボランティアが現地の高齢者に手伝おうかと言われ、「私たちの仕事だ」と何も仕事を渡さなかった話が書いてありました。
これはお互いの立場がありますから、一概にどうと判断できません。
ただし、できることをしっかりと行ってもらうために一歩引いて現地の方に手伝ってもらうこともボランティアの役割の一つであるということ。
目的を持って何かをやってもらう、役割を持ってもらうことは非常に重要。
支援する側は「親切な心で、不親切に対応する」ということも必要です。
介護者がやってあげたら、すぐに終わることをあえて、本人にやってもらう(見守りをした上で、安全の担保をした上で)ことも生活動作のリハビリにつながります。
これは時間がかかるので、ご家族や介護者、介護スタッフですらも忘れがち。
「生活を活発にする」と言うことは実は手間のかかることなのです。
動いたらいい!で終わる話ではなくて、どうしたら動いてもらえるか?動きやすくなるか?ということに目を向けるのも一つのリハビリですね。
スポンサーリンク
阿部洋輔
最新記事 by 阿部洋輔 (全て見る)
- 介護業界での新しい生活様式実践の前に整理したいこと - 2020年5月28日
- 新しい生活様式の感染防止の3つの基本をデイサービスに当てはめてみた - 2020年5月16日
- 宇宙飛行士選抜試験からマネジャーとしての働き方を学ぶ - 2020年5月2日
- 中学受験はいらない - 2020年5月1日
- HYGGEとLYKKEを参考に自分のライフスタイルを考える - 2020年4月29日
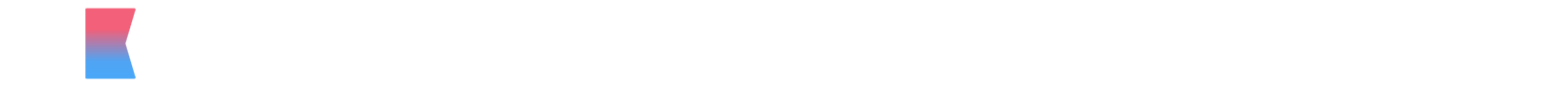


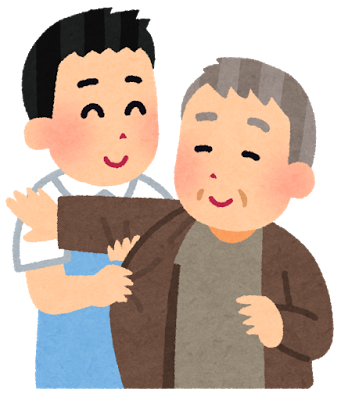

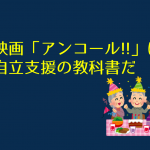
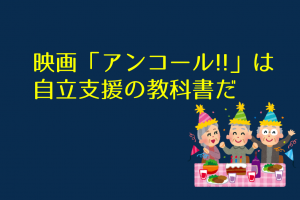
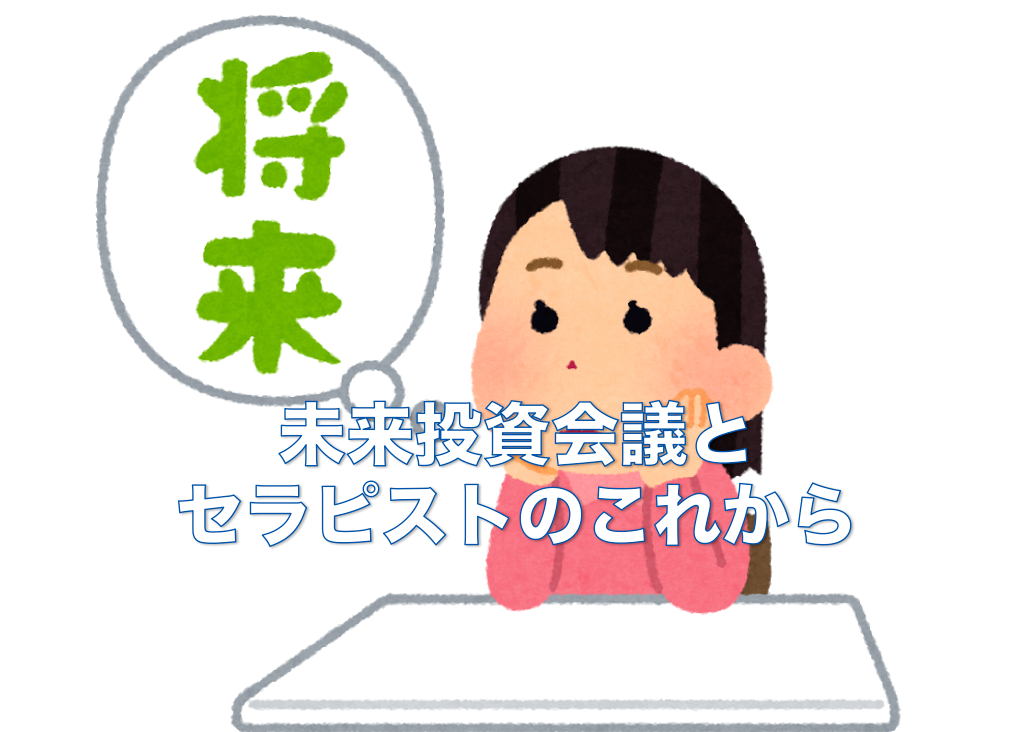
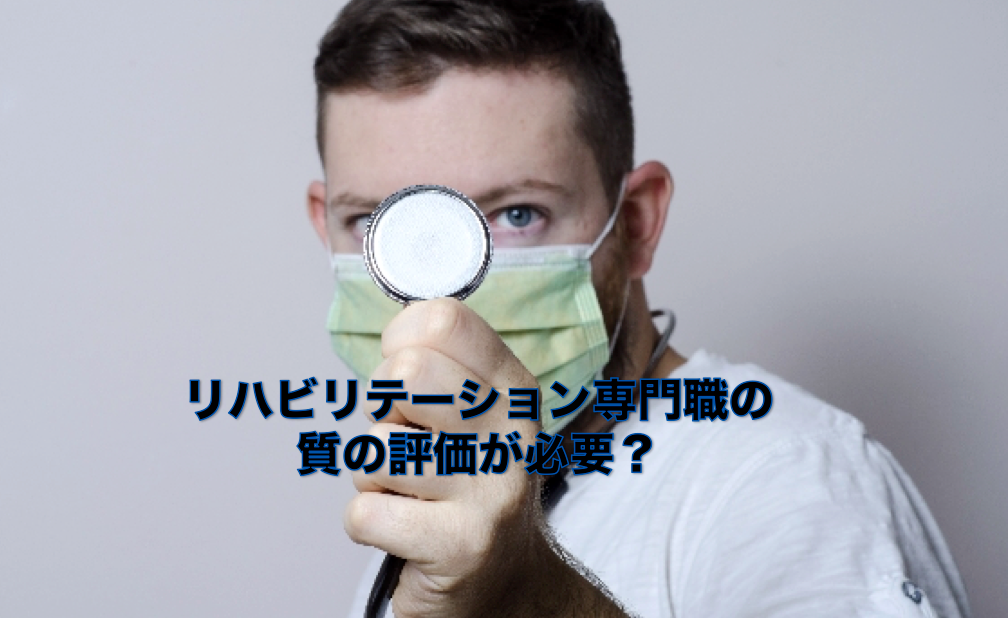

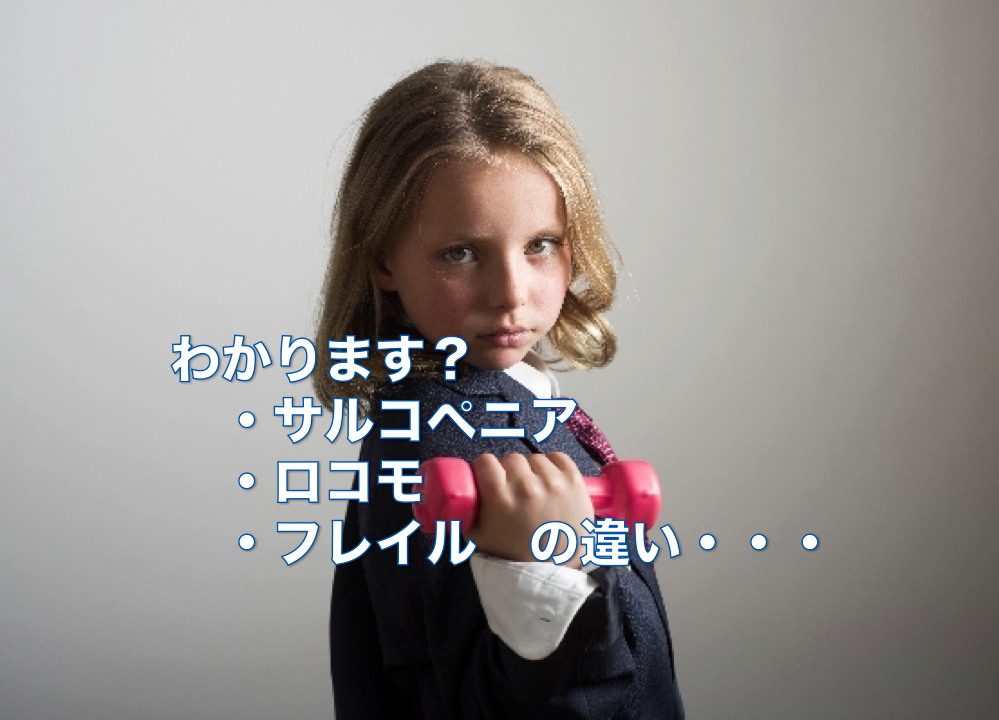
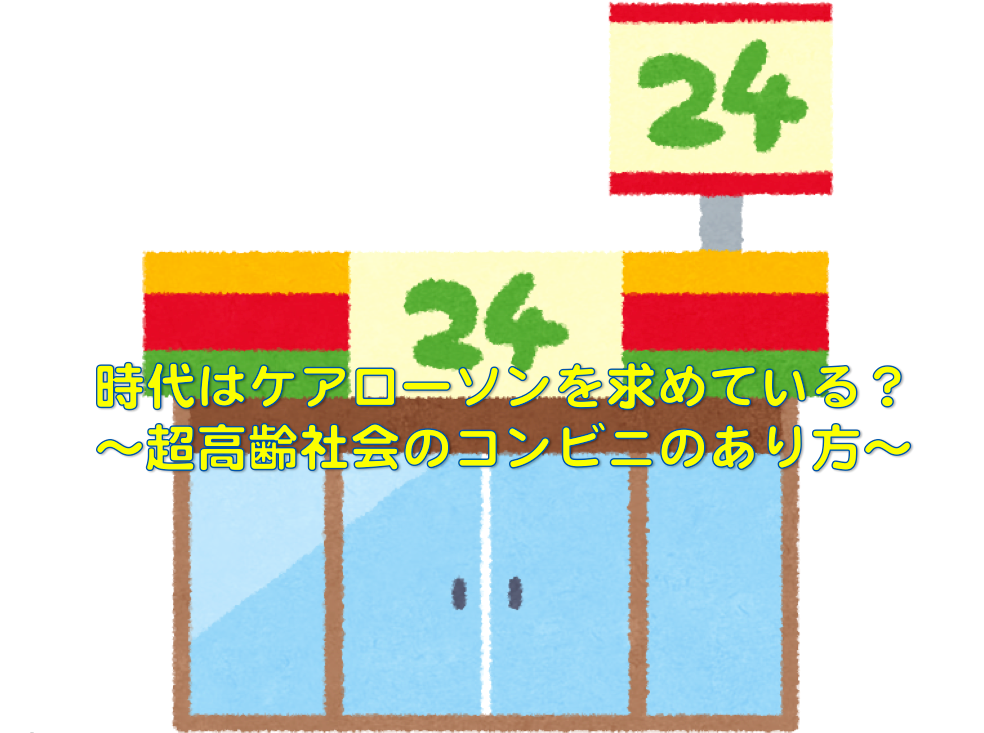
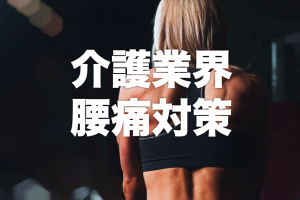

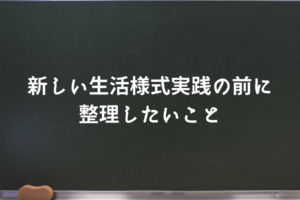













コメントを残す